top of page
会員サイト
ログイン
新規登録
with BRIGHT 会員サイト
日本初のブライダル事業専門の総合法務サービスを提供するBRIGHTの会員サイトです。
(当サイトの閲覧には「ブライダル事業サポーター B-knight」のお申込みが必要です。)


Q.【衣裳持込料】衣裳を提携先からしか選ぶことができないのは独占禁止法に違反、また持込料は消費者契約法第10条により違法なのではないでしょうか?
A.衣裳の持込料が、独禁法に抵触するか、また消費者契約法に抵触するか、について解説します。 1.持ち込み規制が独禁法に抵触するのか? 「独禁法に抵触するのではないか?」とたまに指摘があるのは、同法で禁じている『不当な取引制限』についてです。 しかし、同法第2条第6項では...
2024年9月4日


Q.「持込料」をいただく場合、消費税負担は発生するのでしょうか?
A.税金に関することなので、最終的には、自社の顧問税理士の先生にご確認いただきたいのですが、 一般論として、消費税とは「提供された商品・サービスの対価」に課税されるものですので、 対価性のない支払いには発生しません。 そうなると、この「持込料」の性質が『機会損失・逸失利益...
2023年1月30日


Q.衣裳のお持込の場合に当社では「持込料」という名目でご料金をいただいています。他社様では「保管料」「管理料」などの用語になっていたりしますが、適切な用語はありますか?
A.まず、法律上は「結婚式場における『持ち込み衣裳』預かり」について指す文言はありませんので、 「法律上絶対にこの表現でなければならない」というものはありません。 次に、他社事例でいうと「持ち込み料」というストレートな表現を用いている例は...
2022年10月22日


「持込規制は法律違反」という指摘は本当か?
「持込規制は法律違反」という指摘は本当か? 一般的な結婚式サービスは、ホテル・式場が新郎新婦からその業務を受託した後に、司会、装花、撮影等を担当するパートナーを手配し、新郎新婦にサービスを提供するという形が取られています。...
2020年12月6日
【持込トラブル回避】 Q 「持込」規制についてお客様とトラブルになることが多いのですが、どうすればよいでしょうか?
A 「持込」規制の存在がトラブルになりがちなのは事実であって、BRIGHTとしても非常に多く問い合わせを受けるテーマです。 トラブルの原因は、ズバリ「説明不足」に尽きるケースが多いようです。 ホテル・式場側としては、そのような規制をかけるのであれば、契約前にその内容をしっか...
2020年1月22日


【持込等のルール規制】(5分22秒)説明時に気を付けることは?
「持込規制」「六切り写真データを渡さない」「チャペル内撮影禁止」等のルールを説明するときに気を付けることは?
2020年1月22日
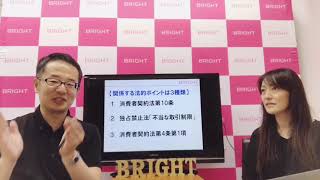
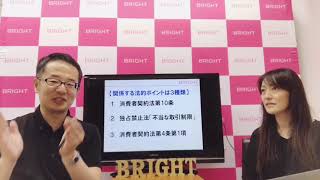
【持込料】(5分45秒)
持込料をとるのは違法なのでしょうか?
2019年12月20日


「持込」問題にどう対処すべきか? 第9回 ブライダル事業者が留意すべき点
ここまで8回にわたり「持込」規制についての考察をしてきましたが、いかがでしたでしょうか? 業界の中にいると当たり前のことも、外部から見ると異様に映ったり、あるいは合理性を疑われたりすることがあり、その典型例として「結婚式契約における持込規制」の問題が、今、取り上げられてきて...
2019年6月22日


「持込」問題にどう対処すべきか? 第8回 新たな設計のあり方についての提言
ここまでの検証をまとめると、以下のように整理できるでしょう。 1.一般的な「持込」規制は、直ちに法律上の問題が生じるものではない。 したがって、どのような規制であろうと、基本的には法的に否定されるものではない。 2、しかし「持込」規制は新郎新婦にとってはその目的が分かりづら...
2019年6月22日


「持込」問題をどう対処すべきか? 第7回 「持込」規制に合理性はあるのか
本稿では会場が「持込」規制を設ける3つの「目的」と、「持込」規制という「手段」との間に客観的な合理性が認められるのか?というテーマについて検討してみます。 第3回で私は、「持込規制」の目的としては、 」 ① 会場の経済的事情 ② 結婚式の円滑な進行...
2019年6月22日


「持込」問題にどう対処すべきか? 第6回 顧客の不満の原因はどこにあるのか
第4回と第5回で明らかにしたように、「持込」規制自体については、直接的に何らかの法律に抵触するという関係性にはありません。 ただ、唯一法的に留意すべき場面としては、「契約締結前に持込規制の内容を正しく伝えていない場合」が挙げられます。...
2019年6月22日


「持込」問題にどう対処すべきか? 第5回 独占禁止法に抵触するのか
「消費者契約法」に続いて、昨今「持込」規制について法律上問題点を指摘されているのが、『「独占禁止法」に抵触するのではないか』という観点です。 前提として整理しておくと、「消費者契約法」とは事業者と消費者との間での契約、つまり会場と新郎新婦との間で締結される結婚式契約について...
2019年6月22日


「持込」問題にどう対処すべきか? 第4回 消費者契約法第10条に違反するのか
第2回で紹介したように、平成30年1月30日付の日本経済新聞夕刊(東京版)は 高額な持込料について、消費者庁消費者制度課は「一般論だが、消費者に一方的な不利益になる取り決めを禁じる消費者契約法に触れる可能性がある」とする。...
2019年6月22日


「持込」問題にどう対処すべきか? 第3回 「持込」規制の目的は何か
そもそも、会場が「持込」を規制する目的はどこにあるのでしょうか。 突き詰めれば、主に3つの目的が導き出せます。 1つ目は、日経記事でも指摘された「経済的事情」です。 会場が提携パートナーに婚礼に関する商品やサービスを外注する際には、提携パートナーに対しては業界用語で「下代(...
2019年6月22日


「持込」問題にどう対処すべきか? 第2回 日経はどう報道したのか
では、平成30年1月30日付の日本経済新聞夕刊(東京版)は「持込」規制についてどのように報道したのでしょうか? まず記事の冒頭で 結婚式の契約を巡るトラブルが相次いでいる。国民生活センターによると、2016年度の相談件数は全国で約1700件に上り、カメラ撮影などを外部の業者...
2019年6月22日


「持込」問題にどう対処すべきか? 第1回 「持込」を巡る近況
ホテルや結婚式場(以下「会場」といいます。)において提供される結婚式サービスは、通常の場合、会場が予め提携する司会、装花、写真撮影、映像製作、着付け、ヘアメイク等の事業者に対して個別の業務を外注し、手配する図式で成り立っています(以下、会場が外注する提携先事業者を「提携パー...
2019年6月22日
【持込・消費者契約法違反】 Q 「持込」規制は、新郎新婦にとっては婚礼の選択肢を奪っているので、消費者契約法に違反するのではないでしょうか?
A 消費者契約法は、新郎新婦などの消費者と事業者間の取引で消費者の利益を保護すること等と目的とした法律で、消費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に害する規定は無効とされています。 しかし、そもそも「持込」の可否はあくまで契約上の設定によるもので、法律上「持込」自体が消費...
2019年4月22日
【持込・独占禁止法】 Q 「持込」規制は、会場提携以外の事業者がビジネスをするチャンスを奪っているので、独占禁止法に違反するのではないでしょうか?
A 確かに、「持ち込み規制は独占禁止法違反だ」との指摘が一部にあります。(以下、独禁法といいます) 独禁法は、事業者間の競争を促進すること等を目的とした法律で、例えば、非常にシェアの高い業者が他の業者を不当に排除しようとしたり(私的独占)、いわゆるカルテルを結んだりすること...
2019年2月22日
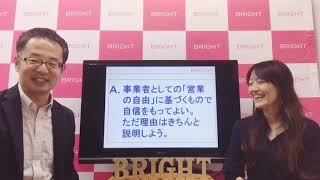
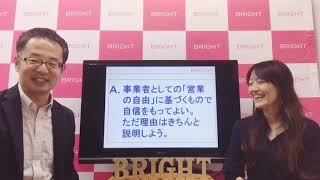
【持込料】(8分5秒)
持込料ってなぜあるの?どう説明?(後半)
2019年2月21日


【持込料】(5分8秒)
持込料ってなぜあるの?どう説明?(前半)
2019年2月21日
bottom of page

.png)
.png)
